2012年12月27日
浜松城天守門整備工事
今年も後わずかですね…。仕事柄、しばらくは休みが取れないので、外出も出来ず、城廻は封印です。でも最後は、やはり地元のお城のことを書かないと…。
去る10月17日、浜松城公園の徳川家康公像前で、浜松城天守門整備工事の安全祈願祭が行われた事は皆さんも良くご存知だと思います。浜松市では古絵図と発掘調査結果をもとに、平成24、25年度の2年をかけて、天守門を原位置に復原するのです。
浜松城の中枢にあたる天守曲輪には、第二代城主、堀尾吉晴の時代に天守が建築されたといわれていますが、江戸初期には喪失しています。天守曲輪の入口に建つ「天守門」は、幕末まで維持されましたが、明治6年(1873年)に解体され、払いさげられました。 天守門は、門の上部に櫓が載る櫓門(やぐらもん)と呼ばれる建物で、櫓門は重要な曲輪の入口に建てられました。

浜松市の「浜松城公園整備」の一環、というか、目玉の一つとして、まずは「天守門」が再建されます。浜松城は確かな天守閣の資料がないためお城も昭和になって建てられた模擬天守です。歴史&戦国ブームで国内各地の史跡では、復元工事や大規模な改修が盛んに行われている中、徳川家康の居城、そして出世城というわりには城の整備が・・・。今まではずっとそんな思いでいましたが、やっと浜松も歴史のまちとしても動き始めたわけです。ゆるキャラの家康くんも全国区に向けて有名になろうとしていますが、ひこにゃんの彦根もくまもんの熊本もお城が一流ですから…是非浜松も…。
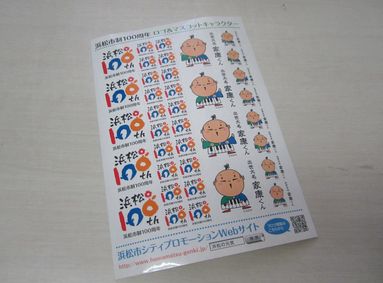
完成は2014年の春だそうです。(富士見櫓も2020年までに再建する計画だそうです)浜松市ば、近年、国民文化祭での「城跡フェスティバル」や昨年の市制100年を記念した数々の「戦国」「城」に関するイベントを開催し、静岡県では一番「戦国時代」で盛り上がっている町といえます。そんな浜松市のシンボル「浜松城」に新たな名所「天守門」が出来るのは、大いに期待したいものです。
そういえば、この天守門。新聞記事などには、建設費が1億6800万円とかありましたが、国産、それも地元の天竜産の木材を使って、櫓門に門の左右の土塀を復元するそうで、その金額は意外に安い…!?計画では、完成後の天守門の内部は展示室になるそうですが、天守門からの光景なども期待したいですね!
さて皆さんは浜松城の天守を誰が建てたかご存知ですか?
「もちろん、徳川家康でしょ!」と言う方がほとんどなのではないでしょうか?
実は浜松城に石垣を築き、天守を建てたのは、徳川家康ではなく、堀尾吉晴という大名なのです。
堀尾吉晴は、尾張国の出身で、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という三人の天下人に仕えました。豊臣政権下では秀吉の重臣となり、秀吉の天下統一を助けました。
吉晴は、小田原の北条攻めのあと、12万石の知行で浜松城主となりました。
浜松在城は、わずか10年でありましたが、吉晴が浜松に残したものは大きなものがありました。私たちが現在見ることの出来る浜松城の石垣は、吉晴が築き、天守台の上に巨大な天守を建てたと考えられています。
堀尾氏は知行地内の二俣城や鳥羽山城も石垣を持つ城へ改修しました。浜松城や二俣城を家康の築いた戦国の城から近世城郭へ大きく変貌させ、豊臣政権の天下を世に知らしめました。
その後吉晴は、関ヶ原の戦いで徳川家康の東軍側につきました。関ヶ原の戦いでは、息子忠氏の活躍もあり、24万石に加増され出雲・隠岐国の国持大名へ大出世しました。


普請上手 松江開府の祖~堀尾吉晴(1543~1611)…
去る10月17日、浜松城公園の徳川家康公像前で、浜松城天守門整備工事の安全祈願祭が行われた事は皆さんも良くご存知だと思います。浜松市では古絵図と発掘調査結果をもとに、平成24、25年度の2年をかけて、天守門を原位置に復原するのです。
浜松城の中枢にあたる天守曲輪には、第二代城主、堀尾吉晴の時代に天守が建築されたといわれていますが、江戸初期には喪失しています。天守曲輪の入口に建つ「天守門」は、幕末まで維持されましたが、明治6年(1873年)に解体され、払いさげられました。 天守門は、門の上部に櫓が載る櫓門(やぐらもん)と呼ばれる建物で、櫓門は重要な曲輪の入口に建てられました。

浜松市の「浜松城公園整備」の一環、というか、目玉の一つとして、まずは「天守門」が再建されます。浜松城は確かな天守閣の資料がないためお城も昭和になって建てられた模擬天守です。歴史&戦国ブームで国内各地の史跡では、復元工事や大規模な改修が盛んに行われている中、徳川家康の居城、そして出世城というわりには城の整備が・・・。今まではずっとそんな思いでいましたが、やっと浜松も歴史のまちとしても動き始めたわけです。ゆるキャラの家康くんも全国区に向けて有名になろうとしていますが、ひこにゃんの彦根もくまもんの熊本もお城が一流ですから…是非浜松も…。
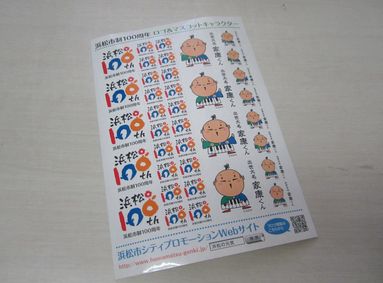
完成は2014年の春だそうです。(富士見櫓も2020年までに再建する計画だそうです)浜松市ば、近年、国民文化祭での「城跡フェスティバル」や昨年の市制100年を記念した数々の「戦国」「城」に関するイベントを開催し、静岡県では一番「戦国時代」で盛り上がっている町といえます。そんな浜松市のシンボル「浜松城」に新たな名所「天守門」が出来るのは、大いに期待したいものです。
そういえば、この天守門。新聞記事などには、建設費が1億6800万円とかありましたが、国産、それも地元の天竜産の木材を使って、櫓門に門の左右の土塀を復元するそうで、その金額は意外に安い…!?計画では、完成後の天守門の内部は展示室になるそうですが、天守門からの光景なども期待したいですね!
さて皆さんは浜松城の天守を誰が建てたかご存知ですか?
「もちろん、徳川家康でしょ!」と言う方がほとんどなのではないでしょうか?
実は浜松城に石垣を築き、天守を建てたのは、徳川家康ではなく、堀尾吉晴という大名なのです。
堀尾吉晴は、尾張国の出身で、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という三人の天下人に仕えました。豊臣政権下では秀吉の重臣となり、秀吉の天下統一を助けました。
吉晴は、小田原の北条攻めのあと、12万石の知行で浜松城主となりました。
浜松在城は、わずか10年でありましたが、吉晴が浜松に残したものは大きなものがありました。私たちが現在見ることの出来る浜松城の石垣は、吉晴が築き、天守台の上に巨大な天守を建てたと考えられています。
堀尾氏は知行地内の二俣城や鳥羽山城も石垣を持つ城へ改修しました。浜松城や二俣城を家康の築いた戦国の城から近世城郭へ大きく変貌させ、豊臣政権の天下を世に知らしめました。
その後吉晴は、関ヶ原の戦いで徳川家康の東軍側につきました。関ヶ原の戦いでは、息子忠氏の活躍もあり、24万石に加増され出雲・隠岐国の国持大名へ大出世しました。


普請上手 松江開府の祖~堀尾吉晴(1543~1611)…
「堀尾吉晴」…通称は「茂助」といい、性格が温和で、容貌も女子のようにやさしかったことから、「仏の茂助」などとよばれていた。しかし、そうした外見の柔らかさ、性格の温厚さとは打って変わって、いざ合戦というときは、厳しく、勇壮な働きをしたと伝えられています。
尾張の出身で、はじめ織田信長に仕え、その後、まだ木下藤吉郎といっていた豊臣秀吉の与力(加勢)につけられます。元亀元年(1570年)の近江横山城攻めのときから正式に秀吉の家臣となり、秀吉が天正元年(1573年)9月、北近江の大名となった段階で150石取りとなって、以後の秀吉の戦いにほとんど従軍し、石高をふやします。
同13年、近江佐和山城主となって4万石を与えられ、近江の大部分を領した豊臣秀次の家老となり、同18年の小田原攻めの後、遠江浜松城12万石に移封され、浜松城をそれまでの土の城から石垣の城に作りかえるのです。
築城名人として加藤清正、藤堂高虎の名前がよく知られていますが、吉晴も普請上手として有名で、「堀尾普請」などという言われ方もしています。普請にかける手間を節約するため、自然地形を最大限に利用しているところに特徴だと言われています。
慶長5年(1600年)の関ヶ原合戦後、出雲・隠岐24万石に加増されたとき、尼子氏の居城だった月山富田城の改修をし、そのあと、「堀尾普請」の集大成ともいうべき松江城の築城に取ります。このときは、城作りだけではなく、新たに城下町作りも行っていて、松江開府の祖は堀江吉晴なのです。
浜松城は別名、「石垣城」旧名「曳馬城」と言われ。「出世城」という異名もあり天竜川以西の遠江を統治する上で、軍事・交通の要衝となる地に位置し、佐鳴湖東部の丘陵を利用した平山城です。
永正年間に、今川貞相が築いた、曳馬城がその前身と言われていますが久野越中守築城説もあるようです。戦国期には、今川家の武将、飯尾氏が治めていましたが、永禄3年(1560)の桶狭間の戦いによって、今川家は衰退し永禄11年(1568)年に、武田家との、駿・遠分割盟約により、徳川家康が遠江に侵攻し、曳馬城を攻略します。その後、元亀元年(1570)、大々的に改修を加え、浜松城と改名しました。
浜名湖の東方の丘陵に、「野面積み」と言われる組み方の石垣を構築し、天守閣・本丸・二の丸・三の丸を一線に並べた、梯郭式という構成になっていて、これに作佐曲輪・出丸を複合的に組み合わせ、堅固な構成となっています。堀には水は通さず、ほとんどが空掘であり、浜松城における、構成上の最大の特徴は、石垣の「野面積み」です。
野面積みは、外見こそ粗雑で、一見すると崩れやすそうに見えるが、奥が深く、また排水性も良いために、耐久性は高いのです。浜松城の石垣は、一部を平成5年(1993)に修復していますが、その多くは、元亀元年築城当時のままだそうです。
尾張の出身で、はじめ織田信長に仕え、その後、まだ木下藤吉郎といっていた豊臣秀吉の与力(加勢)につけられます。元亀元年(1570年)の近江横山城攻めのときから正式に秀吉の家臣となり、秀吉が天正元年(1573年)9月、北近江の大名となった段階で150石取りとなって、以後の秀吉の戦いにほとんど従軍し、石高をふやします。
同13年、近江佐和山城主となって4万石を与えられ、近江の大部分を領した豊臣秀次の家老となり、同18年の小田原攻めの後、遠江浜松城12万石に移封され、浜松城をそれまでの土の城から石垣の城に作りかえるのです。
築城名人として加藤清正、藤堂高虎の名前がよく知られていますが、吉晴も普請上手として有名で、「堀尾普請」などという言われ方もしています。普請にかける手間を節約するため、自然地形を最大限に利用しているところに特徴だと言われています。
慶長5年(1600年)の関ヶ原合戦後、出雲・隠岐24万石に加増されたとき、尼子氏の居城だった月山富田城の改修をし、そのあと、「堀尾普請」の集大成ともいうべき松江城の築城に取ります。このときは、城作りだけではなく、新たに城下町作りも行っていて、松江開府の祖は堀江吉晴なのです。
浜松城は別名、「石垣城」旧名「曳馬城」と言われ。「出世城」という異名もあり天竜川以西の遠江を統治する上で、軍事・交通の要衝となる地に位置し、佐鳴湖東部の丘陵を利用した平山城です。
永正年間に、今川貞相が築いた、曳馬城がその前身と言われていますが久野越中守築城説もあるようです。戦国期には、今川家の武将、飯尾氏が治めていましたが、永禄3年(1560)の桶狭間の戦いによって、今川家は衰退し永禄11年(1568)年に、武田家との、駿・遠分割盟約により、徳川家康が遠江に侵攻し、曳馬城を攻略します。その後、元亀元年(1570)、大々的に改修を加え、浜松城と改名しました。
浜名湖の東方の丘陵に、「野面積み」と言われる組み方の石垣を構築し、天守閣・本丸・二の丸・三の丸を一線に並べた、梯郭式という構成になっていて、これに作佐曲輪・出丸を複合的に組み合わせ、堅固な構成となっています。堀には水は通さず、ほとんどが空掘であり、浜松城における、構成上の最大の特徴は、石垣の「野面積み」です。
野面積みは、外見こそ粗雑で、一見すると崩れやすそうに見えるが、奥が深く、また排水性も良いために、耐久性は高いのです。浜松城の石垣は、一部を平成5年(1993)に修復していますが、その多くは、元亀元年築城当時のままだそうです。
Posted by きくいち at 11:22│Comments(0)
│大将





















